はじめに:セルフジャッジってなに?
テニスの試合って、ジュニアでも「自分たちでジャッジ」するって知っていましたか?
そう、プロのように審判がつくわけじゃないんです。
これを「セルフジャッジ」と言います。
他のスポーツではなかなか見ない制度ですよね。
「入ってたのにアウトって言われた!」よくある悩み
保護者の方からよく聞くのが、こんな声です。
- 「うちの子、入ってたのにアウトって言われたらしくて…」
- 「相手がミスジャッジばかりで、見ていて辛かった」
わかります。
お子さんが一生懸命プレーしているのに、不公平な判定をされたら、親としては胸が痛みますよね。
でも、テニスには「信頼」の文化がある
実はセルフジャッジって、プレーヤー同士の相互の信頼がベースにあるんです。
「相手を尊重する」「自分に厳しくする」っていう価値観を、試合の中で育てていく。
そういう教育的な意味も含まれているのが、テニスの良さでもあります。
とはいえ、ひどすぎるときはどうする?
とはいえ、中には「明らかにミスジャッジを繰り返す選手」もいます。
しかも、常習的にそういう行為をしている場合も…。
そんなとき、親としてどう対応するのがいいのでしょうか?
まずできること:「ロービングアンパイア」に声をかける
試合会場には、多くの場合「ロービングアンパイア(巡回審判)」や「レフェリー(主審)」がいます。
困ったときは、迷わず運営の大人に相談しましょう。
「ちょっとジャッジが気になるのですが…」と伝えるだけでもOKです。
図解:困ったときの対応フロー

- ① 明らかにおかしい → 自分の子どもに冷静に確認
- ② 改善されない場合 → レフェリー or アンパイアに声かけ
- ③ 試合後 → 主催者にフィードバック(冷静に)
「出場させるべきじゃない」という意見について
なかには、「そういう選手を試合に出させるのはおかしい」という意見もあります。
もちろん気持ちはよくわかります。
ただ、ジュニア期は“学びの場”でもあります。
マナーやフェアプレーの大切さを、試合を通じて知っていく。
指導者もすぐに完璧に直せるわけではなく、少しずつ改善していくプロセスがあります。
じゃあ親は何をすればいいの?
保護者としてできることは、以下のようなサポートです。
- ・子どもが感情的になりすぎないようサポートする
- ・試合後に冷静に話を聞いてあげる
- ・必要なら大会本部にフィードバックする
そして何より、正しい行動を応援すること。
正しくジャッジできた自分を褒めてあげる。そんな関わりが、長い目で見てその子の自信につながっていくはずです。
まとめ:大人も一緒に、フェアな環境を育てる
セルフジャッジの難しさは、子どもだけに押しつけるものではありません。
周囲の大人も、できるだけ早く気づいて、冷静に関わることが大切です。
「フェアであろうとする姿勢」を大人が見せることこそが、ジュニアテニスにおいて本当に大切な教育になるのかもしれません。

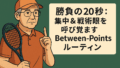
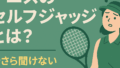
コメント