「セルフジャッジって本当に世界の常識なの?」
テニスの大会に初めて出た保護者の方が驚くポイント。それが「審判がいないのに子どもたちが試合を進めている」という光景です。
これはテニスの基本的なルール「セルフジャッジ(自己判定)」によるものです。
他のスポーツでは審判が必ずいますよね。でも、テニスは違います。それって本当に世界でも同じなのでしょうか?今回は、海外と日本のセルフジャッジ事情を比較しながら、その背景と文化の違いを掘り下げていきます。
セルフジャッジってどういうもの?
セルフジャッジとは、審判のいない試合で、選手が自ら「イン」「アウト」などの判定を行う仕組みです。
特にジュニアの大会では、セルフジャッジが基本となっています。
この制度には、フェアプレー精神を育てるという目的があり、自律や責任感を養う貴重な場でもあります。
🌍 海外と日本のセルフジャッジ運用を比較してみよう

| 国・地域 | 特徴 | 文化・教育背景 | 問題対応 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | The Code(マナー規定)があり、違反はペナルティ。 保護者の介入は禁止。 |
選手に「ルール+倫理」を徹底指導。 コーチも倫理教育の一部。 |
ロービングアンパイアが強く介入し、即時是正。 |
| ヨーロッパ | クラブ文化に支えられた信頼関係。 大会も地域に根ざして運営。 |
幼少期からクラブでマナー教育。 試合は「信頼の文化」で成り立つ。 |
OBやスタッフが自然に見守る体制。 |
| オーストラリア | 年齢・レベルに応じて段階的にセルフジャッジ導入。 | 全豪オープン主催のTennis Australiaが教育リソースを提供。 | トラブルがあれば即座に仲裁。 参加型の教育も積極的。 |
| 日本 | セルフジャッジはあるが、教育やサポートにばらつき。 | クラブや大会によって指導の質が異なる。 文化として浸透していない面も。 |
審判が不在なケースも多く、保護者が感情的に介入することも。 |
📚 実際に見られる教育や文化の違い
- アメリカ:USTAが配布する「The Code」によって、ジュニア選手でも規律を持って行動。
- ヨーロッパ:クラブ内での信頼関係がベース。マナー教育が自然と身につく。
- オーストラリア:Tennis Australiaが動画教材などを通じて、年齢ごとの導入方法を設計。
- 日本:大会によっては審判不在。問題が起きた際の「対応の仕方」がまだ確立されていない。
🧒 子どもの育成視点で見たセルフジャッジの利点
セルフジャッジの最大のメリットは、「正しいことをする」ための判断力や勇気が育まれることです。
誰かに見られていなくても、正しくプレーしようとする意識。それが、人生全体に通じる「信頼される力」を育ててくれます。
💡 日本が学べることは?
ヨーロッパのクラブ文化を見ると、「信頼ベースの運営」が根本にあるとわかります。
つまり、ただルールを教えるのではなく、「信頼できる雰囲気」を周りの大人が作っているのです。
日本でも、「見守る・信じる・手本になる」大人の関わり方が、子どもの行動に影響を与えます。
✅ まとめ:セルフジャッジは、世界のテニス文化そのもの
セルフジャッジは、単なるルールではなく、「テニスを通じて人として成長するための仕組み」です。
世界ではそれが自然と機能している一方で、日本ではまだまだ発展途上。
でも、それは悪いことではありません。これから整えていけば良いんです。
保護者の方にできることは、「信じて見守ること」「困ったときに相談できる環境を用意しておくこと」。
テニスを通じて育つ“信頼の文化”。それは、子どもたちにとってかけがえのない財産になります。

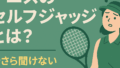
コメント