「入ってたのにアウトって言われた…」
そんな言葉を、試合後に子どもから聞いたことはありませんか?
ジュニアのテニス大会では、なんと選手たちが自分たちでイン・アウトをジャッジします。
これ、セルフジャッジ(self-judging)というルールです。
「いやいや、自分で判定って…それ、もめるでしょ!」と思う方も多いと思います。
実際、他のスポーツではほぼあり得ない仕組みです。
でもテニスでは、これが“当たり前”として世界中で行われているんです。
セルフジャッジってなに? そしてなぜそんな仕組みがあるの?
セルフジャッジとは、審判がつかない試合で、選手たち自身がイン・アウトを判断しながら試合を進めるルールです。
自分のコートに落ちたボールについて、自分でコール(判定)します。
実はこのルール、テニスが「相手を信じること」「誠実さを大切にする」という文化の中で生まれました。
もともとイギリスの貴族の間で発展したテニスは、“紳士のスポーツ”として、「正直であること」「フェアであること」が最も重視されたのです。
子ども同士で判断するって大丈夫?
とはいえ、子ども同士でジャッジをする中で、当然トラブルは起きます。
- 明らかにインだったのに「アウト!」と言われた
- 同じ選手が何度もジャッジを間違える
- 抗議すると「うるさい」と怒られる
そういう話、保護者の間でも「またあの選手だ…」といった噂になることも少なくありません。
でもそのとき、親として「どう対応すべきか」はとても悩ましいですよね。
海外でもセルフジャッジは普通?
実は、セルフジャッジは日本だけではなく、世界中のジュニア大会で導入されています。
アメリカでは「The Code(ザ・コード)」というプレーヤー向けマナーガイドがあり、ルール違反があればペナルティ対象にもなります。
オーストラリアでは年齢別にルールの難易度が変わり、段階的にセルフジャッジ力を育てる仕組みもあります。
つまり、どの国でも「スポーツマンシップを学ぶ教材」として、セルフジャッジが活用されているんですね。
じゃあ日本ではどう? 保護者にできることは?
もちろん、トラブルが起きたときに「見てるだけ」では辛いものです。
でも、感情的になって相手選手やコーチに詰め寄るのは逆効果。
むしろ、試合中にやるべきは以下のようなアクションです。
- 「ロービングアンパイア(巡回審判)」に声をかける
- 冷静に大会運営へ相談する
- 選手自身にも「落ち着いて伝えるように」と声かける
子どもが成長するチャンスに変える
親ができる最も大切なこと、それは子どもがフェアに行動できたことを認めることです。
たとえミスジャッジされても、「あなたはちゃんとルールを守れていた。それが何より大事だよ」と伝えること。
それが、のちの大きな自信や、スポーツを通じた“人間力”になっていきます。
まとめ:セルフジャッジは不完全。でも、だからこそ価値がある
確かに、セルフジャッジは完璧じゃない。
むしろトラブルの種になりやすい。
でも、その“不完全さ”の中に、「信じる」「尊重する」「伝える」というテニスの本質があります。
フェアプレーを教えるには、大人がまず落ち着いて見守ること。
今さらだけど、不思議なこのルールの中に、子どもたちが大切なことを学べる瞬間が詰まっているのかもしれません。
セルフジャッジ。奥が深いルールです。
そして、見守る大人も試される、テニスらしいルールです。


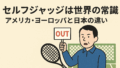
コメント